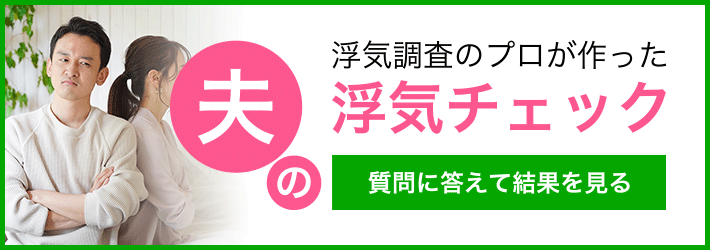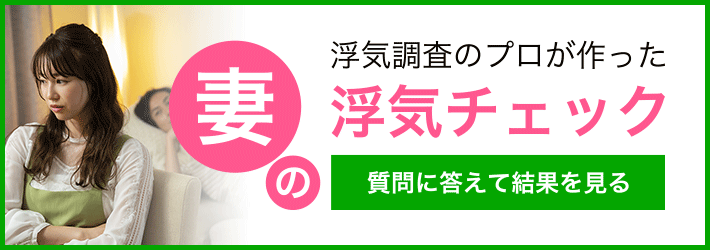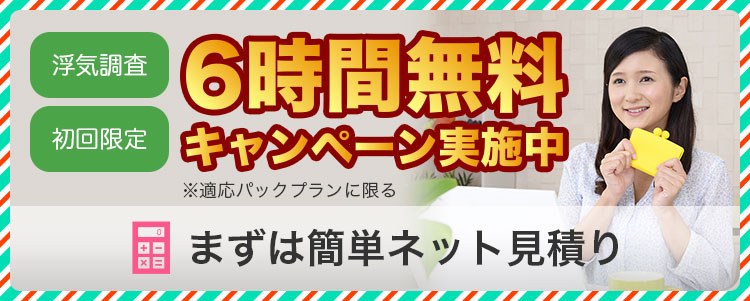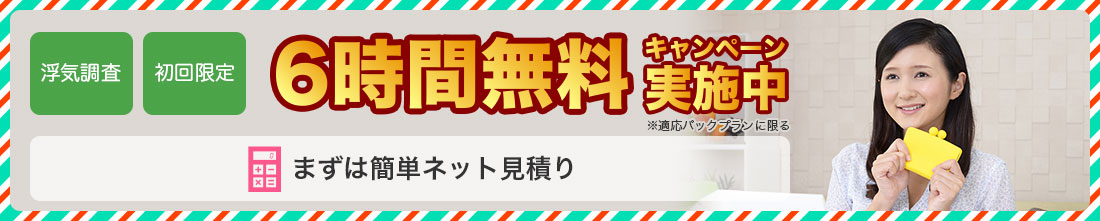その他婚姻費用が払われない…どうする?証拠収集から解決までの最善策

「生活費がもらえず、生活に困っている…」
夫婦が別居していても、生活を維持するために支払われるはずの「婚姻費用」。しかし、支払われない、連絡が取れない、収入が不明など、現実は想像以上に複雑です。
婚姻費用の請求には、「証拠」が必要になる場面が多くあります。
たとえば、相手の収入、生活実態、所在などが不明確な場合、正当な請求が難しくなることも。
この記事では、婚姻費用の基本知識から、問題の背景を整理し、どのような情報が必要になるのかを解説します。
まずは、状況を整理するための一歩を踏み出すことが大切です。
お悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
婚姻費用とは?基礎知識と法律上の位置づけ
婚姻費用とは、夫婦が法律上の婚姻関係にある限り、互いに扶養義務を負うことから発生する生活費の分担を意味します。たとえ別居中であっても、経済的に一方が不利な立場に置かれている場合、もう一方が生活を支える義務を負うと定められており、家庭裁判所などを通じての請求が可能です。
婚姻費用に含まれる主な支出項目は以下の通りです:
食費や水道光熱費などの生活費
子どもの学費や教育費
医療費
家賃や住宅ローンの支払い
子どもの養育費相当分
このように婚姻費用は、単なる生活援助というよりも、婚姻関係を維持するうえで必要不可欠な費用とされ、法律的には明確に権利が認められています。
民法第760条では、夫婦は婚姻中、互いに協力し扶助しなければならないとされており、これは専業主婦(または主夫)であっても当然に認められる権利です。
婚姻費用の定義と法律的根拠
婚姻費用は、夫婦間の扶養義務に基づき支払われるべき費用であり、民法や家庭裁判所の実務でも広く認められています。法的な根拠は以下のとおりです:
民法760条:「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担しなければならない」
これは単なる同居生活の費用だけでなく、別居中の生活維持費も含まれます。
法律上、婚姻費用の支払い義務者は、一般的に収入が高い側とされ、金額の多寡は双方の経済力を基にして決定されます。たとえば、年収差が大きい場合や、子どもの人数・年齢によっても算定額は変動します。
婚姻関係の維持と生活費の分担
婚姻関係が継続している限り、たとえ離婚を前提とした別居であっても、配偶者間の生活の水準をおおむね一致させる必要があります。これは以下の理由からです:
婚姻関係が法的に続いている限り、扶養義務は消滅しない
特に子どもがいる家庭では、子どもの生活水準の維持も重要視される
相手の収入状況が不明な場合でも、調査や交渉によって適正な請求が可能
住宅ローンや医療費、学費などの支出も、生活費の一環として認められるケースがあります。
婚姻費用と養育費・慰謝料との違い
婚姻費用、養育費、慰謝料はすべて家庭問題に関する金銭項目ですが、以下のように明確な違いがあります:
婚姻費用:婚姻中、または離婚が成立するまでの生活費の分担
養育費:離婚後の子どもの生活・教育費を支える費用(親権を持たない側から支払う)
慰謝料:不倫やDVなどによる精神的損害への賠償金
婚姻費用の算定方法と具体例

婚姻費用の金額(支払額)は、夫婦それぞれの収入や生活状況、子どもの人数・年齢などに応じて決定されます。これは主観的に決めるものではなく、家庭裁判所が公表している「算定表」を用いて、ある程度客観的に算出されるのが通常です。
この算定表は、裁判所の審判や調停でも標準的に使われる計算ツールであり、全国の弁護士や法律事務所、弁護士法人でも一般的に参照されます。支払義務者が給与所得者か自営業者かによっても適用される表が異なり、状況によっては加算・控除の調整も必要です。
「いくら支払えばいいのか?」「どのくらい請求できるのか?」というご相談は非常に多いです。
算定表を用いた婚姻費用の計算方法
婚姻費用の金額を決める際は、以下の流れで算出されます:
夫婦それぞれの年収(給与・賞与含む)を確認
子どもの人数と年齢(0〜14歳/15歳以上)を考慮
共働きか専業主婦か、職業や扶養家族の有無を確認
裁判所の算定表に当てはめて目安の月額を把握
例えば、夫が年収500万円、妻が専業主婦で子ども2人(7歳と15歳)の場合、算定表上では婚姻費用の月額はおよそ6〜8万円前後が一般的な目安とされます。もちろん、これには地域や物価、事情による増減の可能性もあります。
収入、人数、年齢などの考慮要素
婚姻費用の算定には、以下のような個別事情が大きく影響します:
収入の種類と安定性:給与、事業収入、不労所得など
子どもの人数と学齢:私立学校や進学先による費用差
住宅ローンや家賃の負担:既存の生活水準を維持するため
医療費や障害などの特別な事情
モラハラ・DVなどで別居せざるを得なくなった場合
これらの要素は算定表だけではカバーしきれない「事情」として、調停や審判の場で裁判所が判断材料として考慮します。
給与所得者と自営業者の違いと対応
給与所得者の場合、源泉徴収票や課税証明書などから収入を確認できますが、自営業者やフリーランスの場合は、実際の収入が不透明になりやすく、正確な算出が難しいことがあります。
そのような場合、以下のような調査・確認が有効です:
売上記録、確定申告書の取得
生活水準(車・住宅・出費)の観察
収入源の多重性(副業、資産運用など)の把握
探偵の調査によってこうした収入の実態を裏付ける証拠を得ることで、裁判所での請求金額に大きな影響を与えることが可能となります。
月額の目安といくらが妥当か
「いくらもらえるのか」「何円支払えばいいのか」という質問はとても多く寄せられます。実際には一律の相場があるわけではなく、前述のように双方の収入、家族構成、生活の水準などによって千差万別です。
しかしあえて一般的な目安を挙げると、以下のような傾向が見られます:
夫婦のうち一方が無収入、子ども1人:月5〜7万円
夫婦ともに収入あり、子ども2人(うち1人高校生):月7〜10万円
子どもが私立学校に在学、または医療費がかかるケース:月10万円以上
このように、月額の金額はさまざまな事情により変動します。明確な目安を知りたい場合は、無料の法律相談や算定ツールの活用も有効ですが、それ以上に客観的な収入データの取得が不可欠です。
婚姻費用請求の流れと手続き

婚姻費用は、夫婦間の話し合い(協議)で合意できれば、比較的スムーズに解決できますが、現実には感情的な対立や経済的事情の違いにより、合意形成が難しいケースが少なくありません。
そのような場合は、家庭裁判所による調停や審判の場で解決を図る必要があります。婚姻費用の請求には、明確な法的手続きが存在し、段階的に進めていくことが求められます。
また、請求を行うためには相手の収入をある程度把握しておく必要があり、調査・準備を怠ると、希望する金額が認められない可能性もあります。
話し合い(協議)による合意形成
最も円滑なのは、夫婦間の話し合いで婚姻費用の金額や支払い方法を決める協議方式です。ここでは以下のようなポイントを明確にしておくとトラブル回避につながります:
月額いくら支払うか(算定表などを基に検討)
支払期間や終了の条件(例:離婚成立まで)
振込口座や支払日などの具体的な方式
支払遅延時の対応(延滞金や慰謝料の扱い)
ただし、口頭の約束だけでは後に「そんな約束はしていない」などのトラブルが起きる恐れがあります。よって、書面化(公正証書の作成など)を強くおすすめします。
調停・審判・裁判所を通じた法的手続き
協議での合意が困難な場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、裁判所の仲介によって解決を図ることになります。流れは以下のとおりです:
申立書と必要書類(戸籍謄本、収入証明など)を提出
調停期日の通知を受けて出頭(平日開催)
双方の意見を聞いたうえで合意形成を目指す
合意に至らなければ審判(裁判官の判断)
この際、双方の収入や支出の内訳、生活実態の証明が極めて重要になります。例えば「収入を過小申告している相手」「資産を隠している配偶者」などの調査が行われていない場合、正当な金額の判断が難しくなるためです。
公正証書・内容証明など書面の活用
婚姻費用の支払いについて合意が得られた場合、その合意内容を明文化しておくことは後の強制執行や履行確保に役立ちます。
特に有効なのが以下の2つの書面です:
公正証書:強制力を持つ執行文が付けられれば、支払いが滞った場合に給与差押えなどが可能
内容証明郵便:相手に対して法的な請求の意思表示を明確に伝えることができる
いずれも弁護士法人や法律事務所を通じて作成するケースが多いですが、必要な情報や証拠の準備が事前にできているかどうかが極めて重要になります。
請求のタイミングと過去分の取得可能性
婚姻費用の請求は、原則として請求した時点からの発生となりますが、状況によっては過去分の遡及請求が認められることもあります。たとえば、
明確に生活費が払われていない状態が継続していた
相手が支払う意思を表明しながらも履行していない
調停・審判の申し立てが長期化している
などの事情があれば、裁判所の判断によって一部過去の期間までさかのぼって支払命令が出ることもあります。ただし、このような判断はケースバイケースであり、正確な資料と客観的証拠が重要です。
婚姻費用を払わない・払ってもらえないとき

婚姻費用は法律上の義務であり、正当な理由なく支払いを拒むことは認められていません。
しかし実際には、「収入が減った」「生活が苦しい」「納得できない」など、支払いを渋る配偶者が存在するのも事実です。
支払ってもらえない場合、感情的に対応することなく、冷静に法的手段を選択することが非常に重要です。
また、状況によっては調査・証拠収集によって、より有利な立場での主張が可能になります。
支払拒否の理由とよくあるトラブル
婚姻費用の支払いを拒否する際、配偶者側からよく挙げられる主張は以下のようなものです:
「自分の生活も苦しい」
「相手が浮気・不倫している」
「もう夫婦関係は破綻しているから不要」
「一方的に別居された」
「支払う義務があるとは思っていない」
これらの主張には法律的な根拠がないケースも多く、感情的なものに過ぎないことがほとんどです。たとえ婚姻関係が破綻していても、離婚が成立するまでは婚姻費用の支払い義務は継続します。
また、こうしたトラブルにはモラハラやDV、経済的支配が背景にある場合も少なくありません。
強制執行や間接強制による対応方法
婚姻費用の支払いについて合意・決定があったにもかかわらず、相手が支払わない場合は、強制執行や間接強制といった法的措置が可能です。
強制執行の主な手段:
給与の差押え(勤務先が把握できている必要あり)
預貯金の差押え
不動産・資産の強制売却(大規模な案件で限定的)
間接強制とは、支払いがなされない場合に金銭的な制裁金を課す方法で、心理的なプレッシャーを与えることで履行を促します。
これらの手続きを行うには、家庭裁判所の審判書や公正証書などの執行力のある文書が必要です。
また、相手の勤務先や口座情報が不明な場合は、実質的に執行が困難になることもあるため、事前の調査が極めて重要になります。
モラハラ・DV・不倫など特殊なケース
婚姻費用の支払い問題が単なる金銭トラブルでなく、モラハラやDV、不倫・浮気などの行為と絡んでいるケースもあります。
たとえば以下のような背景がある場合:
暴力や精神的虐待によって別居を余儀なくされた
不倫の証拠があるにもかかわらず、逆に責任転嫁してくる
相手が故意に収入を隠したり、資産を他人名義にしている
このような複雑な背景事情がある場合、婚姻費用の請求だけでなく、将来的な離婚・慰謝料請求・財産分与にも大きな影響を及ぼします。
婚姻費用と離婚・別居との関係

婚姻費用は、離婚が成立していない状態で夫婦が別居しているときに、収入の多い一方がもう一方に対して支払うべき生活費の補助です。
「すでに別居しているから生活はそれぞれで」と考える方も多いですが、法律上の婚姻関係が続いている限り、扶養義務は維持されるため、婚姻費用の請求は可能です。
支払い義務者となるのは、収入の高い側が原則です。相手が無収入、または低収入の場合は、その生活を維持する責任があると判断されます。婚姻費用は、感情の問題ではなく法律的な義務であることを理解する必要があります。
別居中の婚姻費用の必要性と条件
別居している場合でも、生活費を分担する必要性は変わりません。
婚姻関係にある限り、たとえ同居していなくても次のような条件を満たしていれば、婚姻費用を請求できます。
別居が一方的・違法なものでないこと
相手に支払い能力(収入・資産)があること
自分が無収入または収入が少ない立場にあること
子どもを監護している場合(養育費を含む請求も可)
別居理由がモラハラ、DV、価値観の不一致、不倫などである場合も、正当な理由として認められます。
請求には相手の収入・生活状況などを把握しておくことが重要です。
離婚後の養育費や生活費との違い
婚姻費用と養育費は似ているようで、以下のように明確な違いがあります。
婚姻費用は婚姻中(離婚前)の生活費の分担
養育費は離婚後に子どもの生活費を支払うもの
婚姻費用は夫婦間、養育費は親子間の扶養義務に基づく
婚姻費用は、離婚が成立した時点で終了しますが、養育費は子どもが成人するまで(または大学卒業程度まで)継続して支払う義務があります。
また、婚姻費用には自分自身の生活費も含まれますが、養育費はあくまでも子どものための費用です。
離婚調停・財産分与との関係性
婚姻費用の請求と同時に、離婚調停や財産分与の話し合いが進行しているケースも多くあります。
しかし、以下のような誤解は避けなければなりません。
「離婚調停中だから、婚姻費用の請求はしない方がいい」
「財産分与を受け取る予定なので、婚姻費用はいらない」
「支払いが遅れているのは仕方がない」
婚姻費用と財産分与、慰謝料などはそれぞれ独立した権利です。
婚姻費用は、婚姻関係が終了するまでの生活維持のための支援であり、財産分与とは目的も性質も異なります。
婚姻費用が未払いであれば、離婚成立後に慰謝料や財産分与と合わせて清算する形にすることも可能ですが、原則として別々に請求するべきです。
再婚・親権変更時の婚姻費用の扱い
婚姻費用は離婚が成立した時点で終了しますが、以下のような事情の変化があった場合も、減額や終了の判断がなされることがあります。
請求側が再婚した
子どもの親権や監護者が変更された
請求側に十分な収入があることが判明した
支払い義務者の収入が著しく減少した
ただし、これらは自動的に支払い義務がなくなるというわけではなく、家庭裁判所に申し立てを行い、審判・調停などで正式に決定される必要があります。
また、相手が一方的に支払いを停止した場合でも、正当な手続きを経ていなければ、不履行となり強制執行や損害賠償の対象となる可能性があります。
減額・増額の条件と注意点

婚姻費用は一度決まればずっと同じ金額というわけではなく、当事者の生活状況や収入の変化によって減額または増額が認められる可能性があります。
たとえば、支払い義務者の収入が減った場合、または請求側が新たに収入を得て経済的に自立できるようになった場合などは、再計算が検討されます。
ただし、変更を希望する場合には、必ず家庭裁判所での手続きや合意が必要です。
一方的に金額を変えたり、支払いを停止することは認められません。
生活状況や年収の変化による改定
婚姻費用の減額・増額を認めてもらうには、以下のような客観的な事情の変化があったことが前提となります。
減額が認められる主な理由:
支払い義務者の年収が著しく減少した(転職・失職など)
重大な病気や障害で就労が困難になった
支払い義務者が新たな扶養義務(再婚、子の誕生など)を負った
請求者が就労を始め、収入が増加した
子どもが独立し、扶養が不要になった
増額が認められる主な理由:
請求者の収入が減少または喪失した
子どもが私立学校に進学し、学費や教材費が増加した
医療費など予期せぬ支出が増えた
支払い義務者の収入が著しく増加した
子どもの人数が増えた(出産など)
こうした変更は、過去に取り決めた内容が現状に合っていないときにのみ認められます。
医療費・学費・私立学校の影響
生活にかかる費用の中でも、医療費や教育費は突発的かつ高額になりやすく、婚姻費用の改定理由として重視される傾向があります。
特に私立学校への進学や進学塾、入試対策費用、通学交通費などの出費は、標準的な算定表では想定されていないケースが多く、追加の考慮が必要です。
家庭裁判所ではこうした費用の増加が一時的なものか、恒常的なものかを判断し、必要に応じて加算される可能性があります。
ただし、金額が高ければ必ず増額されるというわけではなく、支払い義務者の収入とのバランスや、合意当初の生活水準も勘案されます。
相手方の再婚や資産の取得があった場合
相手が再婚して新たな配偶者の収入が加わる、あるいは不動産や金融資産を取得したなどの事情があった場合、それが婚姻費用に影響する可能性があります。
ただし、再婚相手の収入が婚姻費用に直接関与するとは限りません。
判断されるのは、主に以下の点です:
再婚後も婚姻費用の支払いが生活に重大な負担を与えるか
新たな家庭を持ったことで、他の扶養義務が発生したか
取得した資産の管理方法や収益性(家賃収入など)
逆に、請求側が不動産を相続したり、保険金を受け取るなどして生活基盤が改善した場合も、減額が検討されることがあります。
これらの情報は、自ら確認することが難しい場合もありますが、調停や審判の際には正確な状況を明らかにすることが求められます。
婚姻費用をめぐるよくある悩みとその解決方法

婚姻費用に関する問題は、単なる金銭トラブルだけでなく、夫婦関係の悪化や子どもへの影響、感情的な対立など、さまざまな悩みを引き起こします。
支払う側・受け取る側の双方にとって、心身ともに大きな負担となることが多く、冷静な対応と情報整理が必要不可欠です。
家庭裁判所の判断を仰ぐにしても、客観的な証拠や事情の説明が求められるため、問題の放置や自己判断による行動は避けるべきです。
夫婦間での感情的対立の対処法
婚姻費用の請求は法的な権利ですが、実際のやり取りでは感情的な対立が障害となるケースが少なくありません。
「支払うお金がない」
「そちらが勝手に出ていったのに払う義務はない」
「そんな話、聞いていない」
といった言い分が多く見られますが、いずれも法律上の義務や判断基準とは一致しない主張です。
このような場合には、第三者を交えて冷静に対応することが有効です。弁護士や家庭裁判所の利用だけでなく、客観的に記録を残すことで、感情的な衝突を避けつつ主張を伝えることが可能になります。
また、電話や通話でのやり取りはトラブルのもとになることが多いため、内容証明郵便や文書での連絡が望ましいです。
子どもへの影響と監護の重要性
婚姻費用が支払われないことで最も大きな影響を受けるのが、子どもです。
特に監護者となっている側が低収入の場合、生活の質が低下し、学費・医療費・食費などが確保できず、子どもの健全な成長に悪影響を与えることもあります。
家庭裁判所では、「子どもの福祉」が最優先されるため、親権や監護者の指定がされた状況では、生活費の一部として婚姻費用の支払いが強く求められます。
親の都合や感情とは切り離して、子どもの権利を守る観点から行動することが大切です。
また、監護者変更の申立てが行われている場合などでは、婚姻費用の支払い状況も考慮材料となる可能性があります。
家庭裁判所での対応と判断基準
婚姻費用に関するトラブルが長期化しそうな場合、家庭裁判所を通じた調停・審判が最も確実な解決手段となります。
裁判所では、以下の点を重視して判断が行われます:
夫婦双方の年収・収入源・扶養状況
子どもの人数・年齢・教育環境
別居理由や生活実態(暴力・不倫・モラハラの有無)
過去の支払い状況と話し合いの履歴
今後の生活設計(進学、再就職など)
これらの情報を整理し、客観的に伝えることが調停や審判を有利に進める鍵となります。
事前に証拠を揃えておくことはもちろん、誤った情報や感情論に流されず、事実を冷静に提示する姿勢が求められます。
依頼すべき専門家(弁護士・法律事務所など)
婚姻費用をめぐる問題が複雑な場合、弁護士や法律事務所に依頼することで、スムーズかつ正当な解決を図ることができます。
以下のようなケースでは、早期の相談が望まれます:
相手が一切連絡を取ってこない・所在が不明
収入の隠蔽や偽装が疑われる
モラハラ・DVがあり、安全に接触できない
過去の婚姻費用が未払いで、強制執行を検討している
調停や裁判所の手続きに不安がある
弁護士法人や地域の法律相談センターでは、初回無料相談や平日・夜間の相談対応を行っているところもあります。
早い段階での相談が、後のトラブル回避と精神的負担の軽減に繋がります。
まとめ
婚姻費用は、別居中や離婚を前提とした状況においても、夫婦の一方が他方の生活を支えるために法的に支払う義務がある費用です。
特に子どもがいる場合は、その養育・教育・医療に必要な費用も含めて生活全体を維持するためのものであり、夫婦関係の破綻や感情的な対立とは切り離して冷静に対応する必要があります。
この記事で解説してきたとおり、婚姻費用に関する問題には以下のような多くのポイントが関係します。
婚姻関係が継続している限り発生する生活費の分担
裁判所が公表する算定表をもとにした金額の算出方法
減額・増額が認められるための条件や手続き
支払いがない場合の法的対応(強制執行・審判など)
地域によって異なる判断傾向や生活実態の違い
弁護士や法律事務所への相談・依頼の重要性
また、相手が収入をごまかしている、所在がわからない、感情的に話が通じないなどの問題がある場合には、早期に第三者を交えて法的に対応することが不可欠です。
「我慢すればいつか払ってくれるだろう」といった希望的観測は危険です。
婚姻費用の未払いが続けば、生活が破綻するだけでなく、将来の養育費請求や財産分与、慰謝料請求にも影響を与える可能性があります。
まずは一歩踏み出して、正しい知識と適切な手段で自分と子どもの生活を守る行動を始めましょう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
HAL探偵社の浮気チェック
調査成功率97.3%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上