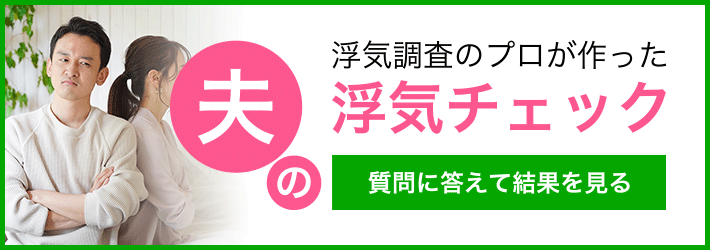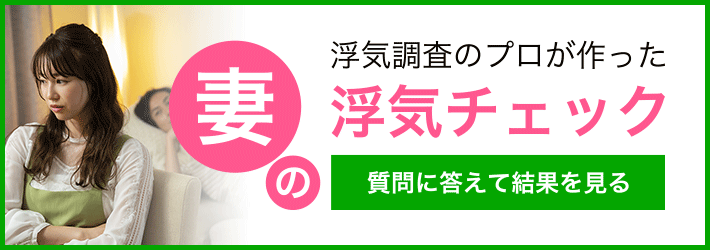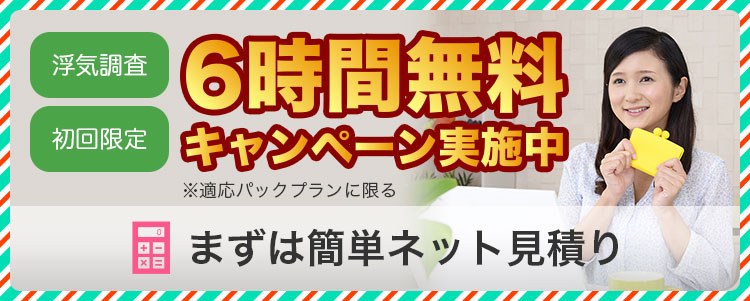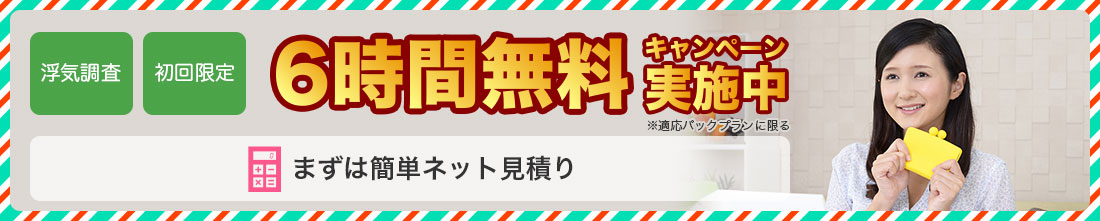その他熟年離婚における財産分与を有利に進めるには?退職金や年金について解説!法律事務所への相談も視野に

「夫が浮気しているみたいだけど、離婚したら財産分与はどうなるのか?」――こうした相談が探偵事務所に寄せられることは少なくありません。特に熟年夫婦の妻からの相談が増えているのが最近の傾向です。
「熟年離婚」という言葉を目にしたことがある人も多いでしょう。明確な定義はありませんが、一般的に50代以上の夫婦が離婚することを指します。
若い頃の離婚と違い、熟年離婚では財産分与が重要なポイントとなります。長年にわたり築き上げた財産をどう分けるのか、老後の生活に影響するため慎重な判断が必要です。
この記事では、熟年離婚の特徴や財産分与の基本について詳しく解説します。離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 数字で見る熟年離婚の増加
熟年離婚に関する記事や報道は以前より増えており、今では決して珍しい話題ではありません。
厚生労働省の「平成30年(2018) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2018年の婚姻件数は586,438組に対し、離婚件数は208,333組。単純計算すると3分の1以上の夫婦が離婚していることになります。
さらに、同居期間20年以上の夫婦による離婚に注目すると、熟年離婚の増加が顕著に見て取れます。
1985年(昭和60年)の離婚総数は166,640組、そのうち同居期間20年以上の夫婦の離婚は20,434組
2018年(平成30年)の離婚総数は208,333組、そのうち同居期間20年以上の夫婦の離婚は38,539組
つまり、1985年から2018年の間に離婚総数は41,693組増加し、そのうち同居期間20年以上の夫婦の離婚は18,105組増えています。
これを割合で見ると、1985年には離婚全体の約12.2%が熟年離婚でしたが、2018年には約18.5%に増加していることがわかります。
このデータからも、近年は熟年離婚の割合が増えていることが明らかです。長年連れ添った夫婦でも、離婚を決意するケースが増えている背景について考えていくことが重要です。
2. 熟年離婚が増加する4つの理由
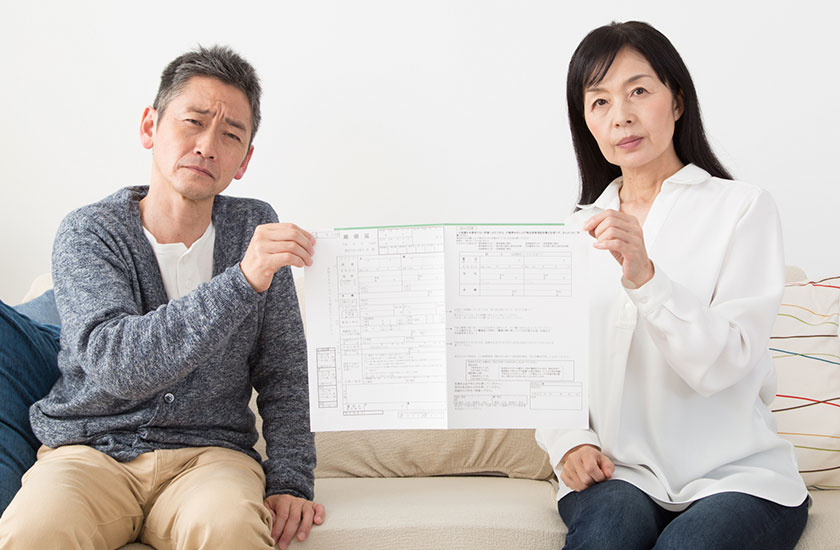
熟年離婚が増えている原因は、一言では説明できません。しかし、近年の社会変化やライフスタイルの変化が影響していることは間違いありません。
ここでは、熟年離婚が増えている4つの主な理由について解説します。
2-1. 共働きの増加が熟年離婚を後押しする
夫が働き、妻が専業主婦という家庭では、経済的な不安から離婚を決断しにくい傾向がありました。しかし、現在は共働きが当たり前の時代になり、妻も安定した収入を得ているケースが増えています。
そのため、**「離婚しても生活できる」**という自信を持つ女性が増え、離婚という選択が現実的なものになっていると考えられます。
2-2. 人生100年時代と「自分らしく生きる」選択
「人生100年時代」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。平均寿命が延びたことで、「自分らしく生きたい」と考える人が増えているのも、熟年離婚が増加している理由の一つです。
子育ても終わり、50代・60代を迎えたときに、「このまま残りの人生を夫(妻)と過ごすべきか?」と考える人が増えています。
「これからの人生は、自分のために生きたい」
「もう相手のために我慢するのはやめよう」
こうした考えから、新しい人生を選ぶ人が増えているのかもしれません。
2-3. 長年の不満が積もり積もって離婚へ
特に大きな出来事があったわけではなく、長年の小さな不満が積み重なった結果、離婚を決断する人も少なくありません。
結婚当初は「あばたもえくぼ」といわれるように、相手の短所も愛おしく感じられるものです。しかし、長年一緒にいるうちに、短所ばかりが気になるようになり、不満が積もりに積もって限界を迎えることもあります。
「性格の不一致」による離婚は、芸能人の離婚理由としてもよく聞かれますが、熟年夫婦にも同じことが当てはまるのです。
2-4. 浮気・不倫がきっかけで熟年離婚に至るケース
熟年離婚は、必ずしも前向きな理由で決断されるわけではありません。
長年連れ添った夫婦のどちらかが浮気や不倫をし、それが発覚したことが原因で離婚を決意するケースも珍しくありません。
特に、「夫が定年退職して家にいる時間が増えたことで、浮気が発覚する」といったケースもあります。
浮気・不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料の金額は、不貞行為の証拠や婚姻期間、精神的苦痛の度合いによって異なります。
浮気や不倫は、年齢を問わず夫婦の関係を破綻させる原因になります。熟年離婚の理由としても、かなりの割合を占めているのです。
3. 財産分与と退職金

熟年離婚を考える際に、財産分与について知っておくことは非常に重要です。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分けることを指します。
しかし、実際には「貢献度」を厳密に評価することは難しく、基本的には「夫婦の共有財産は半分ずつ分ける」のが原則とされています。
特に退職金は、熟年離婚における財産分与の中でも大きな割合を占めることが多く、支払い時期や金額によって扱いが異なります。
ここでは、退職金に関連する財産分与のポイントを詳しく解説します。
3-1. 退職金をすでに受け取っている場合
定年退職後に退職金を受け取り、それが残っている場合、財産分与の対象となります。
財産分与の計算式
退職金総額 × (婚姻期間 ÷ 勤続年数) × 1/2 = 財産分与の対象額
例えば、退職金が3,000万円で、勤続年数40年、婚姻期間30年の場合は以下のように計算されます。
3,000万円 ×(30年 ÷ 40年)× 1/2 = 1,125万円
この金額が、財産分与の対象となる退職金の額です。
なお、婚姻期間とは通常「同居期間」を指します。退職金の正確な金額が分からない場合は、雇用契約書や就業規則を確認することが大切です。
3-2. 退職金がまだ支払われていない場合
退職金が未払いであっても、将来的に支給されることが確実視される場合は、財産分与の対象となる可能性が高いです。
しかし、以下のような条件によって、財産分与の対象外となることもあります。
勤務先の規定で、退職金の支給が明記されているか(就業規則に記載がなければ、支給されない可能性がある)
勤務先の経営状況が悪く、退職金がカットされる可能性があるか
パートナーの転職回数が多く、退職金の積立期間が短い場合
退職金の支給まで10年以上かかる場合(現実的な財産とみなされないことがある)
ポイント
退職金はすべての企業で支給が義務付けられているわけではないため、財産分与を前提に考える場合は、就業規則を確認することが不可欠です。
3-3. 退職金の種類(退職一時金と退職年金)
退職金には、大きく分けて**「退職一時金制度」と「退職年金制度」**の2種類があります。
退職一時金制度
定年退職や自己都合退職の際に、一括で支給される退職金制度
財産分与の対象になりやすい
退職年金制度
退職後、定期的に年金のように支給される退職金制度
財産分与の対象になる場合とならない場合がある
企業によっては退職金制度がない場合もあるため、離婚時に退職金を財産分与の対象とするかどうかは慎重に確認する必要があります。
3-4. 退職金制度の実態
東京都産業労働局が発表した「中小企業の賃金・退職金事情(平成30年版」によると、以下のような調査結果が出ています。
退職金制度がある企業:71.3%
退職一時金のみ:75.9%
退職年金のみ:3.4%
退職一時金と退職年金の併用:20.6%
このデータから、退職金制度のある企業は約7割ですが、退職年金制度を導入している企業は少ないことが分かります。
また、東京都内の中小企業では、3割近くの企業に退職金制度がないため、退職金を前提とした財産分与が必ずしも可能ではないケースもあることを理解しておくことが大切です。
4. 退職金以外に財産分与の対象となる財産【不動産】

財産分与の対象は退職金だけではありません。
夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、基本的に財産分与の対象となります。例えば、給料からの貯金、夫婦の共有名義で購入した車、不動産なども含まれます。
ここでは、財産分与の対象となる「不動産」について詳しく解説していきます。
4-1. 不動産を売却して得られた金額を2分割する方法
不動産は現金のように簡単に分割できません。そのため、不動産を売却し、その売却益を分け合う方法が一般的です。
具体的な流れは以下の通りです。
不動産(家や土地)を売却する
売却益で住宅ローンを完済する(ローンが残っている場合)
売却にかかる手数料などを差し引く
残った金額を夫婦で2分割する
この方法は、特にどちらも家を持ち続けることを希望しない場合に有効です。
また、住宅ローンの残債が売却額を上回る(オーバーローン)場合は、売却しても借金が残る可能性があるため、慎重な判断が求められます。
4-2. 一方が不動産を取得し、財産価値の半分を支払う方法
不動産を売却するのではなく、どちらか一方が不動産を取得し、その価値の半分をもう一方に支払うという方法もあります。
この方法では、次のような点に注意が必要です。
不動産の市場価値を客観的に評価すること(不動産鑑定士に依頼するケースもある)
ローン残高が不動産価値を超えている場合は、財産分与の対象にならないこと(オーバーローン状態では財産としての価値がないため)
取得する側が、財産価値の半分を支払う資金を確保できるかどうか
この方法は、夫婦のどちらかが引き続きその家に住み続けたい場合に適しています。
例えば、夫が家を取得し、妻に対して財産価値の半分を支払う場合、その支払い方法としては現金や預貯金を充てるほか、住宅ローンを借り換えて妻の持分を買い取る方法などがあります。
不動産の財産分与は慎重に!専門家のアドバイスも活用しよう
不動産の財産分与は、市場価値の評価やローン残高の確認など、専門的な判断が必要です。
特に、金銭面で折り合いがつかない場合は、不動産鑑定士や弁護士に相談することで、公平な評価を得られ、納得のいく分配が可能になります。
離婚後の生活に大きく影響する重要なポイントなので、慎重に判断することが大切です。
5. 退職金以外に財産分与の対象となる財産【車】

車も不動産と同様に、婚姻期間中の収入で購入した場合は、名義人にかかわらず夫婦の共有財産となります。そのため、財産分与の対象になります。
5-1. 車の財産分与の方法
車の財産分与の方法は、不動産の場合と同様に、主に2つの方法があります。
車を売却し、売却益を分割する方法
一方が車を取得し、その評価額の半分を他方に支払う方法
どちらの方法を選択するかは、車の利用状況やローンの残高などを考慮して決定されます。
5-2. 車の評価額の算出方法
車の評価額を決める際には、**「レッドブック」**を使用することが一般的です。
レッドブックとは?
有限会社オートガイドが発行する「オートガイド自動車価格月報」の別名
自動車の平均取引価格を年式やグレード別にまとめた冊子
業界(自動車・損保・法曹・官公庁)向けの資料だが、一般人でも入手可能
購入方法はオートガイドのウェブサイトで確認できる
レッドブックはプロ向けに作られた資料で、自動車業界・損害保険業界・法曹関係・官公庁などで広く活用されています。しかし、一般の人でも入手可能です。
レッドブックの購入方法については、オートガイドのウェブサイトに掲載されているため、必要な場合はそちらを確認するとよいでしょう。
このレッドブックを活用することで、公正な市場価値をもとに車の財産分与額を決定できるため、夫婦間のトラブルを避けることができます。
5-3. ローンが残っている場合の注意点
車のローンが残っている場合は、評価額とローン残高のバランスが重要になります。
評価額 > ローン残額の場合 → 財産分与の対象となる
評価額 < ローン残額(オーバーローン)の場合 → 財産分与の対象外
つまり、車の市場価値よりもローン残高のほうが多い場合は、財産として分与できないことになります。
5-4. どの方法を選ぶべきか?
どちらの方法を選ぶかは、車を引き続き使用したいか、ローンの支払い状況はどうかなどを考慮して決める必要があります。
車を手放してもいい場合 → 売却して売却益を分割するのがスムーズ
車を引き続き使用したい場合 → 評価額を算出し、半額を支払う方法を検討
6. 退職金以外に財産分与の対象となる財産【その他】

不動産や車のほかにも、財産分与の対象となる資産があります。ここでは、預貯金・生命保険・隠し財産について解説します。
6-1. 預貯金の財産分与
婚姻期間中に貯めた預貯金は、基本的に夫婦の共有財産とみなされます。そのため、別居時または離婚時の残高を2分割して財産分与の対象とします。
結婚前の貯金は「特有財産」となり、財産分与の対象外
婚姻期間中に増えた分が対象
別居時や離婚時の口座残高をもとに計算
もし、一方が預貯金を無断で引き出していた場合でも、離婚時の財産分与の対象になるため、不当な引き出しが発覚すれば請求することが可能です。
6-2. 生命保険の解約返戻金
生命保険に加入している場合、解約返戻金があるかどうかがポイントになります。
解約返戻金がある場合は、別居時または離婚時の金額を2分割
掛け捨て型の生命保険には解約返戻金がないため、財産分与の対象外
契約者貸付(保険を担保に借り入れ)がある場合は、その金額も考慮
解約返戻金の額は、保険会社に問い合わせることで確認可能です。
6-3. 隠し財産が発覚した場合は?
財産分与の際に、一方が意図的に財産を隠していた場合はどうなるのでしょうか?
夫婦の共有財産を隠すのは不適切であり、本来はフェアではない
財産分与の請求は「離婚時から2年以内」に行う必要がある
2年を過ぎてから隠し財産が発覚しても、請求はできない
つまり、離婚後2年以内であれば、隠し財産に対して財産分与を請求できるということになります。しかし、そもそも隠し財産を持たないことが最も重要です。
7. 財産分与がまとまらない場合の対処法

熟年離婚では、財産分与の話し合いがスムーズに進まないケースも少なくありません。
離婚自体の話し合いが難航することもありますが、財産分与はお金や資産が絡むため、より感情的になりやすい問題です。
もし、話し合いがまとまらない場合は、以下のステップで解決を目指します。
7-1. まずは財産分与について話し合う
財産分与の基本は、まず夫婦間で話し合うことです。
お互いに隠し事をせず、すべての財産を明確にした上で、公平に分ける方法を検討しましょう。
話し合いのポイント
財産のリストを作成し、お互いに確認する
分割方法を決める(売却・現金化・取得など)
後々のトラブルを防ぐため、離婚協議書を作成する
離婚協議書は、口約束だけで済ませず、きちんと書面に残すことが重要です。
「離婚協議書 書き方」でインターネット検索すると、作成方法の参考になる情報が見つかるでしょう。
7-2. 話し合いがまとまらない場合は「離婚調停」を申し立てる
夫婦間の話し合いがまとまらない場合、**家庭裁判所の「離婚調停」**を利用する方法があります。
離婚調停のメリット
第三者(調停員)が間に入るため、冷静に話し合える
直接顔を合わせず、個別に調停室へ呼ばれるため、感情的になりにくい
調停員が意見を整理し、双方が納得できるように調整してくれる
特に感情的な対立が激しい場合、夫婦だけで話し合いを続けるよりも、離婚調停を利用するほうがスムーズに進むことが多いです。
7-3. 離婚調停でもまとまらない場合は「離婚裁判」へ
離婚調停でも合意に至らない場合、最終的には離婚裁判で決着をつけることになります。
離婚裁判のポイント
裁判では「話し合い」ではなく「争う」ことになる
裁判官が証拠をもとに判断し、財産分与を決定する
裁判には時間と費用がかかるため、最終手段として考える
もし未成年の子どもがいる場合、養育費や親権の問題も絡んでくるため、できるだけ早い解決が望まれます。
財産分与についてお互いの主張が平行線をたどる場合は、裁判で決着をつけたほうが、長引かずに済むこともあります。
あわせて読みたい:浮気?離婚?気になるなら親権と監護権の違いも知っておくべき
まとめ
ここまで説明してきたように、熟年離婚の財産分与は簡単にまとまらないことが少なくありません。
長年連れ添った夫婦だからこそ、お互いに言いたいことが多く、感情的になりやすいものです。
しかし、財産分与の問題を先延ばしにすると、離婚後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
円満に財産分与を進めるために
冷静に話し合い、財産を整理することが大切
公平な分配を意識し、感情的にならないよう注意する
話し合いが難航する場合は、専門家のサポートを受けるのも一つの手
もし熟年離婚を考えている、または財産分与を有利に進めたいと考えているなら、探偵事務所や法律事務所、弁護士事務所に相談してみるのも良い選択肢です。
専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズに問題を解決し、新たな人生を前向きに歩むための準備ができるでしょう。
HAL探偵社では、熟年離婚や財産分与に関するご相談を受け付けています。
「パートナーが浮気しているかもしれない…」
「離婚を考えているけれど、財産分与をどうすればいいのかわからない…」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひHAL探偵社にご相談ください。
専門の調査員が的確なアドバイスを提供し、あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
HAL探偵社の浮気チェック
調査成功率97.3%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上