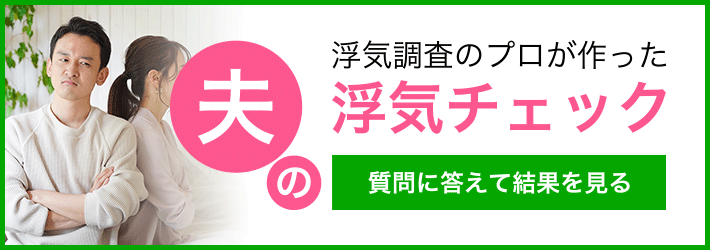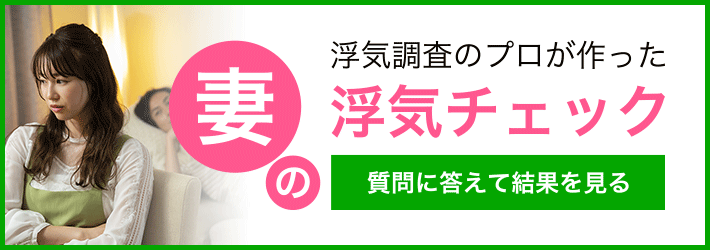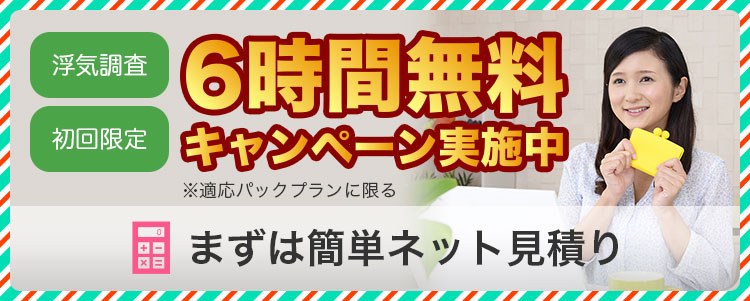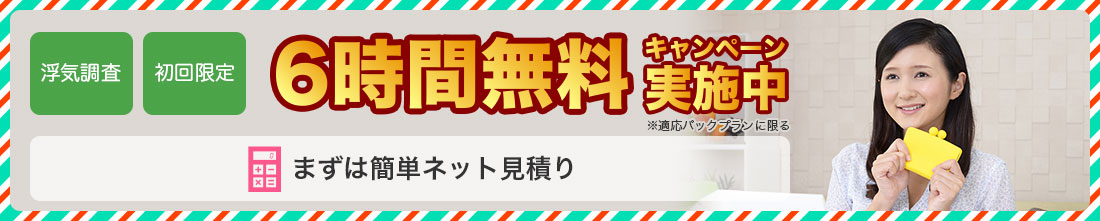浮気/不倫の調査不倫の時効はいつ?慰謝料請求が無効になる前に知っておくべき法律知識

「不倫が発覚した。でも、慰謝料を請求するには“時効”があるって本当?」
配偶者の裏切りに心を痛める中、法律の壁に阻まれてしまうケースも少なくありません。不倫の慰謝料請求には明確な時効が存在し、一定の期間を過ぎてしまうと、どんなに明白な証拠があっても請求が認められない可能性があります。この記事では、不倫の時効がいつから始まり、どれくらいの期間有効なのかをわかりやすく解説し、今すぐ取るべき行動についてもご紹介します。
不倫と時効とは?基本を解説
不倫(浮気・不貞行為)に関するトラブルは、精神的苦痛だけでなく、離婚や財産分与、親権問題にも発展する重大な事案です。
被害を受けた側が慰謝料を請求するには、法律上の権利(請求権)が認められており、民法に基づいて時効が適用されます。
しかし、この「時効制度」には厳格なルールがあり、期限を過ぎると慰謝料を請求できない可能性があります。
特に以下のような方は注意が必要です。
配偶者の不倫に気づいてからしばらく時間が経過している
加害者(不倫相手)の素性や住所がわからない
離婚後に慰謝料を請求したいと考えている
このような状況でも、正しい知識と証拠の確保、そして適切な手続きによって、慰謝料の請求が可能になるケースもあります。
ここでは、不倫と時効の関係性について、法律の観点から詳しく解説していきます。
不倫・浮気と法律上の「不貞行為」の意味
日常的には「浮気」や「不倫」という言葉が使われますが、法律上では「不貞行為」と定義されています。
これは、婚姻中の配偶者が第三者と性的関係を持つことで成立し、民法709条に基づく不法行為として慰謝料請求の対象になります。
主な不貞行為の例:
ラブホテルに出入りしている証拠(写真・動画など)
LINEでの性的関係を連想させるやり取り
通話履歴や音声データの保存
第三者(相手方)との宿泊履歴
ただし、LINEや通話履歴が証拠と認定されるには、性的関係の存在が強く推認される内容である必要があります
これらの証拠をもとに、不貞行為があったことを裁判所で立証できれば、損害賠償として慰謝料を請求する権利が発生します。
証拠が曖昧だったり、不十分だったりすると、たとえ事実として不倫があっても請求が認められない可能性があります。
また、不倫相手が既婚者であることを知っていた、もしくは知ることができた場合には、その相手にも加害者としての責任が生じます。
慰謝料請求が可能なケースとは
不倫の慰謝料請求が認められるには、一定の条件があります。 不法行為があったという事実と、その影響で被害を受けたという精神的苦痛の証明が必要です。さらに、民法で定められた消滅時効の期間も重要です。
請求が認められやすい典型的なケース:
配偶者と不倫相手に肉体関係があった明白な証拠がある
婚姻関係が継続しており、不倫によって破綻したと判断される
子どもや家族関係に悪影響が出た
離婚や離婚調停に発展した
逆に、以下のようなケースでは慰謝料が認められにくい、もしくは減額される可能性があります。
婚姻関係がすでに破綻していた(別居状態など)
配偶者が不倫を認め、示談が成立している
請求の時効期間が過ぎてしまっている
時効は原則として「不倫の事実および加害者を知ってから3年以内」とされており、最長でも不倫行為から20年で完全に請求権が消滅します(これを除斥期間といいます)。 したがって、「10年前の不倫」でも、発覚したのが最近であれば請求が可能な場合もあるということです。 これらの点を理解し、証拠の収集や弁護士への相談を早めに行うことが、時効を迎える前に権利を行使するための第一歩になります。
調査成功率97.3%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上
不倫の慰謝料請求における時効の基本

慰謝料請求において最も重要となるのが「時効」の考え方です。知らずに過ごしてしまうと、権利が消滅してしまい、請求すらできないという事態も起こりえます。
不倫や浮気が原因で精神的苦痛を受けた場合、その損害を回復するための法的手段はありますが、時効の制度に則って進行する必要があります。
ここでは、慰謝料請求の時効の基礎知識として、「起算点」「消滅時効」「除斥期間」などの用語を丁寧に解説し、どのような手続きを踏めば請求が成立するのかを説明していきます。
消滅時効の起算点と期間
不倫の慰謝料請求は、民法第724条の規定に基づく不法行為による損害賠償請求となります。このときの「時効」は以下の2つの要素で構成されます。
被害者が損害および加害者を知った時点から3年
不法行為の時点から20年
このうち、前者は「起算点」と呼ばれ、加害者(不倫相手)の名前や住所、行為の内容を知った日から3年間が時効期間としてカウントされます。
ただし、発覚のタイミングが曖昧な場合や証拠が不十分な場合には、裁判所が起算点を判断する基準が分かれることもあります。
また、後者は「除斥期間」と呼ばれ、たとえ加害者を知らなかったとしても、行為があってから20年が経過すると権利は完全に消滅します。
これを過ぎると、裁判を提起しても訴え自体が却下されるため、非常に重要なタイミングとなります。
不法行為による損害賠償請求の原則(民法第724条)
民法724条には、次のように記載されています。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
つまり、慰謝料の請求は、被害に気づいてから3年以内、かつ不倫があってから20年以内に行わなければなりません。
この点は、弁護士や法律事務所に相談し、状況を把握した上で手続きを進めることが非常に重要です。
とくに、離婚後に慰謝料を請求したい場合は、すでに時間が経過していることも多く、今が請求できる最後のチャンスである可能性もあります。
婚姻関係の破綻や離婚が成立していない場合の注意点
不倫の慰謝料を請求する際、婚姻関係の状況も重要な判断材料となります。
すでに夫婦関係が破綻していた場合、あるいは離婚が成立している場合には、請求の可否や金額に影響を及ぼす可能性があります。
例えば:
別居中でも婚姻関係が破綻していない場合は、慰謝料請求が認められることが多い
夫婦間で合意が成立しているケースでは、請求が難しくなることもある
協議離婚後に不倫が発覚した場合でも、時効内であれば請求は可能
また、熟年離婚などでは、長年の夫婦関係や財産分与、年金分割など複雑な事情が絡むため、専門の弁護士法人への相談が推奨されます。
各地域(関東・関西・九州など)に在籍する法律事務所や探偵社が対応している場合もあるので、地域密着型の事務所の選択も有効です。
慰謝料請求の実務と時効の中断・援用

不倫に関する慰謝料請求では、「時効が迫っている」または「すでに経過してしまった」場合でも、一定の条件を満たせば請求の可能性を保てる場合があります。そのためには、中断や援用のルールを正しく理解し、適切な手続きをとることが重要です。
この章では、時効の中断や援用の制度、そしてそれらを活用して権利を守るための方法について、具体的に解説します。
時効の中断(催告・承認・裁判の提起など)
まず、時効には「中断」という制度があり、適切なアクションを取ることで一時的にカウントをリセットできる仕組みです。中断が成立すれば、時効期間は再スタート(リセット)されます。
中断の代表的な方法は以下の3つです:
催告(内容証明郵便などによる請求の通知)
承認(加害者が慰謝料の支払いを認めた場合)
裁判の提起(調停・訴訟・仮処分・仮差押えなど)
たとえば、慰謝料を請求する意思を内容証明で加害者に送付すれば、その日から6ヵ月以内に正式な裁判手続きを行うことで時効が中断されます。これは、民法第153条および第147条で定められた手続きです。
また、相手方が請求に対して「払う意思がある」と発言したり、LINEで認めたりすれば、それが承認とみなされ、時効はその時点から再度スタートとなります。
ポイント:
中断の通知は書面(内容証明郵便)で行うのが原則
単なる口頭のやりとりでは証明が困難になるため注意
調停や裁判の提起は弁護士と協力して行うのが安心
援用による時効の成立とその効果
逆に、加害者側が「時効が過ぎた」と主張することで請求を無効化することもできます。これを「援用(えんよう)」といいます。
援用は、以下のようなタイミングで使われます:
請求者が裁判を起こしたが、相手方が「時効だ」と主張した場合
書面や弁護士を通じて、加害者が正式に援用の意思を表明したとき
この主張が裁判所に認められれば、慰謝料請求は無効(消滅)となります。
つまり、時効を過ぎているにもかかわらず請求を続けると、却って相手から反論(援用)されてしまうリスクがあるのです。
対応策としては:
時効が近づく前に弁護士へ相談
請求時期の記録や証拠を残しておく
相手方と交渉する場合は、書面に残すことが重要
時効が争点になるケースは、非常にデリケートであり、法的な判断や手続きに強い弁護士法人に依頼することが成功の鍵となります。
内容証明郵便や書面での催告方法
内容証明郵便は、慰謝料請求において非常に有効な手段です。
これは、「誰が、いつ、どんな内容を、誰に送ったのか」が郵便局によって証明される仕組みで、法的効力を持つ証拠としても活用されます。
内容証明を送る際のポイント:
相手の住所・氏名・関係性を正確に記載する
慰謝料請求の理由(不倫・精神的苦痛・不貞行為)を明記
支払い期限や対応方法も記載(例:「〇〇日以内に連絡または支払うこと」)
弁護士が作成した文面で送付するのがベスト
この書面を送付した日が催告日となり、そこから6カ月以内に訴訟・調停などを開始すれば、時効の中断が成立します。
ただし、この期間中に何の手続きも行わなければ、中断は無効となってしまいます。
また、内容証明の文面が不適切であると、相手方に誤解や不信感を与えてしまうこともあるため、できるだけ専門家の監修や作成代行サービスを活用するのが安全です。
時効が成立する前に行うべき対処法
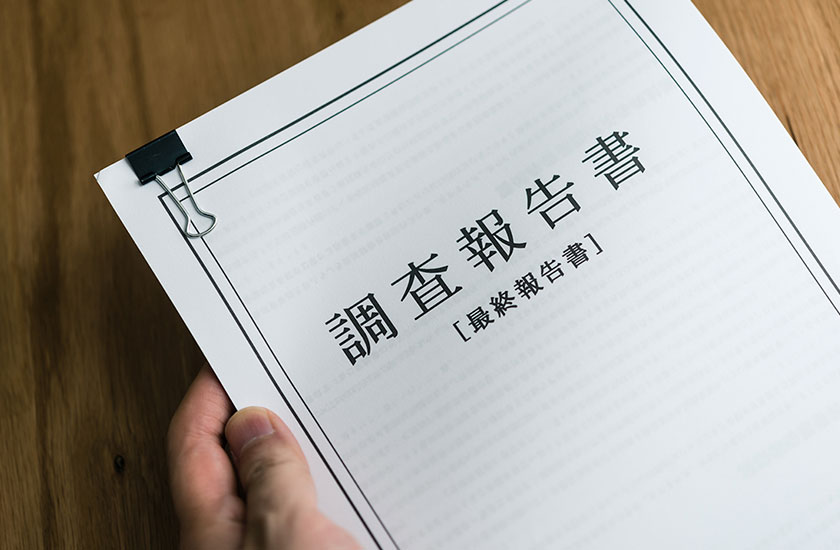
時効の制度や中断の仕組みを理解したうえで、実際に慰謝料請求を成功させるためには、早期の行動と証拠の確保が不可欠です。不倫という事実を知ったとき、精神的ショックから「少し落ち着いてから対応しよう」と先延ばしにしてしまう方も少なくありません。
しかし、時効のカウントは待ってくれません。この章では、時効を迎える前に確実に請求を行うために必要な準備や手段、弁護士への相談の進め方など、実践的なステップを解説します。
証拠の収集(LINE・写真・通話記録など)
まず、慰謝料請求を行う上で最も重要な要素が証拠です。法律上「不貞行為」があったことを示すには、客観的な資料が必要です。
証拠の例:
LINEのやり取り(日付・内容・送信者が明確なもの)
ホテルや旅行に出かけた写真・レシート
音声データや録音
通話履歴やSNSの投稿
探偵事務所による調査報告書
これらは、裁判所が判断を下す際の重要な材料になります。特に、配偶者が不倫を否定している場合、証拠がなければ訴訟に進めないケースも多いため、事実を客観的に示す資料の保管が極めて重要です。
また、証拠が揃っていない場合でも、HAL探偵社のような調査会社に依頼することで、証拠収集が可能です。
弁護士への相談・法律事務所の選び方
証拠が揃った段階で、次に行うべきは法律の専門家である弁護士への相談です。個人で交渉や書面作成を進めることもできますが、失敗すれば逆にリスクを背負うことになりかねません。
弁護士に相談するメリット:
状況に応じた法的判断が得られる
相手との交渉や書面の作成を代行してもらえる
裁判や調停への対応も一貫して任せられる
近年では、離婚問題に特化した「離婚弁護士」や「男女問題専門の法律事務所」も増えています。弁護士法人ALGやアディーレ法律事務所など、特定の分野に強みを持つ法律事務所を選ぶのも一つの方法です。
また、地域密着型の事務所を選ぶことで、面談や来所がスムーズになり、交通費や時間の負担も軽減されます。
法律事務所を選ぶ際のポイント:
初回相談が無料かどうか
不倫・離婚案件の取り扱い実績
弁護士の得意分野や対応エリア(関東・関西・九州など)
加害者や配偶者との交渉・調停・裁判の流れ
証拠と法的サポートが揃えば、いよいよ相手との交渉に入ります。まずは話し合い(任意交渉)での解決を試み、それが難しければ調停、さらに訴訟へと進むのが一般的です。
慰謝料請求の流れ:
加害者や配偶者に内容証明郵便を送付
任意交渉(話し合い)で和解を目指す
交渉決裂時は家庭裁判所へ調停申立て
調停不成立なら民事訴訟を提起
裁判所の判決により金額が確定
強制執行・仮差押などで支払を回収
調停や訴訟では、精神的苦痛の程度、婚姻期間、過去の事情、不倫相手の素性などが考慮され、金額や支払方法が決定されます。
慰謝料の相場はケースによりますが、50万円〜300万円程度が一般的で、悪質なケースでは500万円を超える判決も存在します。
調停や訴訟は時間と費用がかかる可能性がある一方、確定判決を得られれば強制執行も可能となり、確実な支払回収が期待できます。
不倫の慰謝料請求における注意点とリスク

不倫の慰謝料請求は、法律上の正当な権利とはいえ、実際に手続きを進める中でさまざまなリスクや注意点が存在します。 相手の対応次第ではトラブルに発展したり、請求が認められなかったりするケースもあるため、戦略的かつ冷静に対応することが必要です。
この章では、実際に慰謝料請求を行う際に直面しやすい問題や落とし穴を整理し、どのように備えるべきかを具体的に解説します。
相手方の素性が不明な場合の対処
不倫の加害者(不倫相手)に慰謝料を請求するためには、相手の名前・住所などの基本情報が必要です。しかし、配偶者がその素性を隠していたり、LINEやSNSでのみ接触していた場合、相手の情報が分からないことも少なくありません。
対処法:
探偵事務所による調査で相手方の情報を特定
配偶者に直接確認し、録音や記録を残す
弁護士を通じて配偶者に開示請求を促す
証明が困難な場合のリスクと対応策
慰謝料を請求する際、単に「不倫された」と主張するだけでは足りず、不貞行為の事実を証明する責任(立証責任)は請求者側にあります。
証拠が不十分だと:
慰謝料が大幅に減額される
請求が認められない
相手から逆に名誉毀損で訴えられる可能性もある
対応策:
証拠の精度を高める(複数の証拠を組み合わせる)
探偵や弁護士を活用して法的に有効な証拠を確保
LINE・写真・音声などは改ざんされないよう保存方法に注意
また、法律事務所の監修を受けて証拠の有効性を事前に確認することで、裁判や調停でも有利に進めることができます。
精神的苦痛と慰謝料の金額相場
慰謝料の金額は一律ではなく、さまざまな事情が考慮されて決定されます。
判断基準:
婚姻期間の長さ
不倫が原因で離婚に至ったかどうか
子どもへの影響や家庭の状況
不倫の悪質性(継続期間や頻度など)
一般的に、50万〜300万円が相場とされており、悪質なケースでは500万円以上の判決もあります。
一方で、婚姻関係が破綻していたと判断されると、請求が認められなかったり、慰謝料が大幅に減額されたりするリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
また、精神的苦痛が大きく、カウンセリングや医療機関での記録がある場合は、慰謝料額が増額される傾向があります。 そういった資料も証拠の一部として提出可能です。
不倫時効を巡るよくある質問(Q&A)
不倫の慰謝料請求や時効に関しては、ネットや知人からさまざまな情報が飛び交い、どれが正しいのか判断に迷うこともあります。 ここでは、これまでの内容を踏まえ、実際に多くの方が抱える疑問にQ&A形式でわかりやすく解説していき
「10年前の不倫」でも慰謝料請求はできる?
可能な場合もあります。
重要なのは、「いつ不倫の事実と加害者を知ったか」という起算点です。たとえ行為が10年前でも、配偶者のスマホから発覚したのが最近であれば、発覚時点から3年以内なら請求可能です。
ただし、行為から20年が経過していた場合は、除斥期間により完全に請求権が消滅します。
ポイント:
起算点を正しく把握する
発覚した証拠(LINEの日時など)を残しておく
専門家に時効計算を依頼するのも安心
離婚後の慰謝料請求はもう遅い?
遅くはありません。
離婚の有無は時効とは直接関係がなく、不倫の事実を知った日から3年以内であれば、離婚後でも請求可能です。
むしろ、離婚によって精神的苦痛が明確になった場合は、請求が認められやすくなる傾向にあります。
注意点としては、離婚時に「慰謝料を請求しない」という合意書や示談書にサインしていた場合、その内容が有効となることがあります。
こうした書面を取り交わす前には、弁護士などの専門家に相談することが必須です。
調停や訴訟での証拠提出はどんな方法がある?
裁判所では、証拠の形式や提出方法にルールがあります。代表的なものは以下のとおりです。
LINEのスクリーンショット(時刻・送信者が明確なもの)
探偵報告書(日付・場所・行為の記録が詳細なもの)
録音・動画データ(不倫の関係性や会話の記録)
医師の診断書(精神的苦痛があることの裏付け)
これらを提出する際は、証拠能力を損なわないように保存・提出形式に注意する必要があります。
また、証拠の一部を補強するため、複数の資料を組み合わせて提出するのが理想的です。
いずれのケースでも、証拠の価値を最大限に活かすためには、法律事務所など専門家のサポートが不可欠です。
まとめ
不倫に対する慰謝料請求は、精神的苦痛を受けた当事者が正当な権利として行使できる重要な法的手段です。しかしその一方で、時効や証拠の不備、交渉の失敗などによって、請求が認められないケースも多く存在します。
この記事では以下の重要なポイントを解説してきました。
不倫は法律上「不貞行為」とされ、慰謝料請求の対象となる
請求には民法上の時効(3年)と除斥期間(20年)がある
時効は「加害者と損害を知った時点」からカウントが始まる
時効の中断・援用・催告など制度を正しく使えば請求の可能性は残る
証拠の質と量が慰謝料の成否を大きく左右する
弁護士や探偵など専門家と連携すれば、成功率が大幅に向上する
慰謝料請求は、お金を取り戻すだけではありません。自分の尊厳を守り、過去の裏切りに対して「けじめ」をつける行為でもあります。
そのためには、冷静かつ法的に正しいアプローチを選び、期限内に行動を起こすことが非常に重要です。
証拠の収集や加害者の特定が難しい場合でも、諦める必要はありません。
HAL探偵社は、全国対応・年中無休・秘密厳守で調査を行い、証拠の確保から報告書作成まで対応しています。
もし今、配偶者の不倫や離婚、慰謝料請求について悩んでいるなら、時効が成立する前に行動を起こすことが、将来後悔しないための鍵です。
HAL探偵社へお気軽にお問合せください。浮気調査のプロとして、あなたの再スタートを全力でサポートします。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
HAL探偵社の浮気チェック
調査成功率97.3%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上