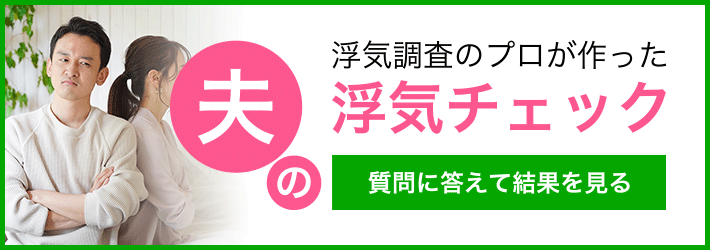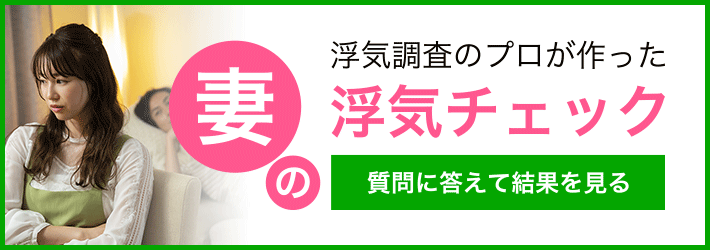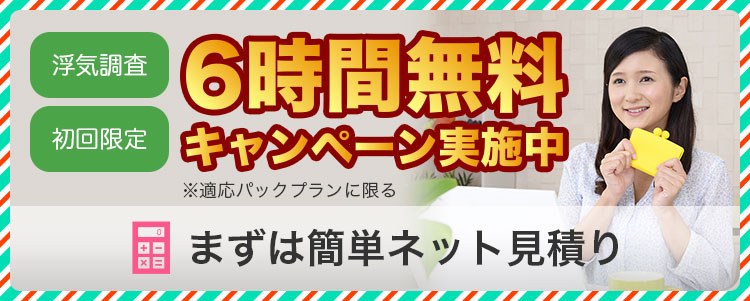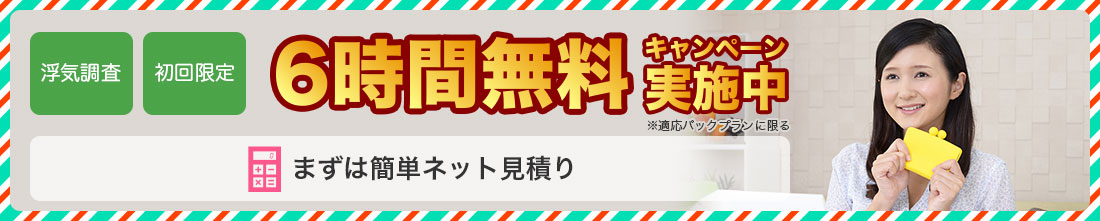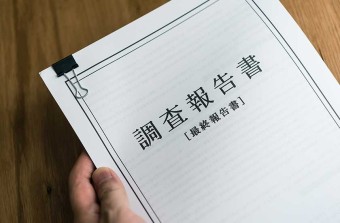その他「最近、売上が合わない…?」従業員の不正調査で見えてくる真実とは

「最近、在庫が合わない」「売上の数字がおかしい」「従業員の様子がどこか変だ…」
そんな違和感を抱いたまま放置していませんか?
実は、企業の内部不正の約7割が“従業員によるもの”だと言われています。
小さな不正が会社の信用や利益を大きく損なうことも珍しくありません。
「まさか、うちの会社に限って…」と感じたその瞬間こそ、調査を始めるタイミングです。
企業に潜む「従業員不正」というリスクとは
企業における従業員不正は、組織にとって深刻な経営リスクとなりえます。
近年では、内部告発やSNSでの情報流出をきっかけに、社内で起きていた不正行為が公になり、社会的信用を失うケースも少なくありません。
企業が内部で抱えるリスクの中でも、「従業員による不正行為」は特に発見しにくく、かつ深刻な損害を引き起こす可能性があります。
たとえば、横領、情報改ざん、取引先との癒着、業務の私的利用などが該当し、いずれも取引や経営に直接的な悪影響を及ぼす行為です。
発覚が遅れる理由の一つとして、「信頼していた社員がまさかそんなことをするはずがない」という思い込みがあります。
しかし、その油断こそが被害の拡大を招き、損害は金額だけに留まらず、ステークホルダーや株主、消費者との信頼関係の崩壊にまで発展します。
従業員不正が引き起こす代表的な問題には、次のようなものがあります:
金銭的損失:横領や架空請求による経済的被害
情報漏洩:社外への機密情報流出や改ざん
社内の混乱:不正行為発覚による社内関係の悪化
社会的信用の喪失:公表・報道によるブランド価値の毀損
法的責任:損害賠償請求や懲戒処分に伴う裁判リスク
こうしたリスクを回避するためには、内部監視体制の整備や、不正の早期発見と対応が不可欠です。
企業法務に明るい弁護士や調査専門家と連携しながら、社内ルールの策定、内部通報制度の整備、調査体制の導入を図ることが求められます。
従業員不正の種類と具体的な手口

従業員不正と一口に言っても、その手口や範囲は多岐にわたります。
不正行為は、社内のあらゆる部門や業務に潜む可能性があり、経理部、人事部、営業部など、それぞれの役割と立場に応じて異なる形で現れます。
また、不正は金銭目的だけでなく、私的な感情や利害関係者との癒着など、背景にある理由もさまざまです。ここでは代表的な不正行為の種類を紹介し、その実態と対策について詳しく解説します。
横領・金銭の不正管理
企業にとって最も多い不正行為の一つが「横領」です。
特に、経理部門や売上を管理する部門では、現金や振込業務を扱う機会が多く、不正が発生しやすい土壌があります。
よくあるケース:
売上金の着服
架空取引先への振込と、その金額の流用
経費精算の水増し申請
これらの行為は日常業務の中で自然に行えるため、社内での発見が遅れがちです。
したがって、金銭の流れを定期的に監査し、複数人での承認フローを設けることで、不正の芽を摘む体制構築が重要です。
対応策としての例:
承認ルールの整備と記録保全の徹底
調査対象を広く取り、パソコン・メールの履歴も分析
社外の監査法人による不定期な調査実施
データ改ざん・情報漏洩
デジタル社会においては、情報の改ざんや漏洩といった行為も深刻な問題です。
社員が業務で得た顧客データや機密情報を社外に持ち出す、またはSNSで拡散するなどの行為は、企業に重大な不利益をもたらします。
事例として多いもの:
USBメモリによる情報の持ち出し
社内文書や資料を無断で複製・送信
他部署のアクセス権を不正に利用し、データを改ざん
フォレンジック調査を通じて、パソコンやサーバーの記録を解析する方法も、こうした不正の発見に有効です。
特に、ログ記録を残す仕組みの導入やアクセス管理の厳格化は、情報漏洩防止の第一歩です。
業務時間の虚偽報告・SNS不正利用
勤怠システムの不備やリモートワークの増加により、労務管理の甘さを突いた不正行為も急増しています。
具体的な手口:
実際は出勤していないのに「勤務中」として打刻
営業訪問と偽って私用で外出
勤務中に私用SNSを利用して社内情報を発信
このような労務に関する虚偽申告は、本人だけでなく上司や管理部門の監督責任にも発展する可能性があります。
証拠をもとにした対応が必要となるため、調査チームによる記録の収集やヒアリングが重要です。
社外関係者との癒着・取引先との不正取引
従業員と取引先や外部パートナーとの癒着や不正な取引関係も、企業にとって見過ごせないリスクです。
これは特に、購買部門・営業部門など社外と日常的に接する社員に起きやすい傾向があります。
該当する不正行為の例:
特定の取引先に便宜を図る見返りに金銭や接待を受け取る
不正な契約条件を設けて自社に損害を与える
架空取引で経費を不正支出させる
こうした行為が発覚した場合、契約無効や損害賠償請求に発展し、裁判や社外委員会による調査が行われることもあります。
企業側は、契約書の内容を定期的にチェックし、必要に応じて法律事務所や弁護士法人の支援を受けることが効果的です。
従業員不正が発覚する流れと初動対応
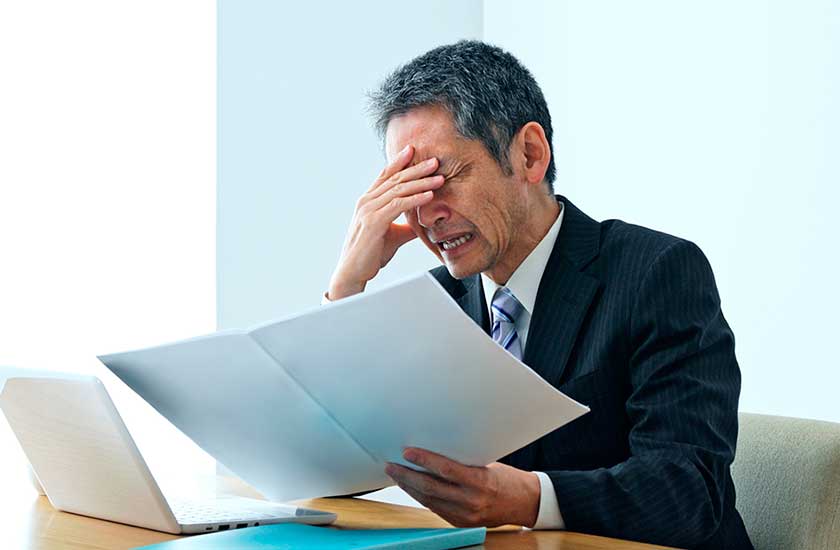
従業員による不正行為が発覚するまでには、いくつかの典型的なパターンがあります。
突然の内部告発や帳簿とのズレ、不審な行動など、最初は小さな違和感から始まることが多く、その段階での判断と対応が被害の拡大を防ぐ鍵になります。
企業としては、不正発覚の初期段階から社内調査や外部専門家への依頼を視野に入れる必要があります。
初動対応が適切であれば、証拠の保全、社内外の混乱抑止、責任追及の明確化が可能になります。
不正発覚のきっかけと内部通報制度の役割
社内不正の発覚で最も多いのが「内部通報」です。
上司や同僚、あるいは匿名の第三者からの通報をきっかけに、不祥事が明らかになるケースは非常に多くなっています。
公益通報者保護法により、通報者の保護が企業に義務付けられたこともあり、通報窓口の設置と制度の整備は必須事項です。
適切な内部通報制度の運用は、不正防止と早期発見に直結します。
内部通報制度の整備ポイント:
通報窓口を社内と社外の両方に設置する
匿名での通報も可能にし、通報者を保護
対応状況を随時フィードバックし、信頼性を高める
社員への周知と定期研修の実施
このように、通報制度が整備されていれば、不正行為の早期発見が可能となり、企業の損害を最小限に抑えることができます。
不正行為発見から調査依頼までの流れ
不正が疑われる段階で重要なのが、迅速かつ慎重な初動対応です。
疑わしい社員に直接問い詰めるなどの軽率な行動は、証拠の削除や口裏合わせ、さらなる改ざんを誘発するリスクがあります。
そのため、まず行うべきは「社内で事実を把握・整理し、専門家の協力を仰ぐこと」です。
この段階でHAL探偵社など外部の専門調査チームに調査を依頼することは、非常に効果的です。
初動対応のポイント:
担当部署(人事、総務、コンプライアンス部門)で状況を整理
証拠となり得る資料やデータ(パソコン、メール、帳簿など)を保全
不正の影響範囲と関係者をリストアップ
弁護士や調査専門家との連携体制を構築
この初期のステップでの証拠の記録・保存は後の処分判断や損害賠償請求にも大きく影響します。
社内調査と外部調査の選択
企業が不正調査を実施する際、社内調査だけで対応すべきか、外部調査を依頼すべきかの判断は非常に重要です。
社内調査のメリット:
社内事情に詳しく、迅速な情報収集が可能
コストが比較的安価に抑えられる
社内調査のデメリット:
客観性・中立性に欠けると捉えられがち
調査対象者との利害関係により適切な判断ができないリスク
一方、外部調査(HAL探偵社など)を利用するメリットは以下のとおりです:
第三者による中立的で客観的な調査が可能
フォレンジック技術を活用した専門的なデジタル調査が行える
社員や役員に対するヒアリングの実施・報告書作成まで対応
調査結果をもとに弁護士と連携した法的対応が可能
企業規模や案件の性質に応じて、調査方法を柔軟に検討する必要があります。
特に、不正の影響が外部の取引先や株主にまで及ぶ可能性がある場合、外部調査の導入が望まれます。
不正調査の実施方法と調査対象の範囲

従業員による不正行為が発覚した場合、企業としては迅速に調査を実施し、事実関係を明らかにする必要があります。
この調査には、「いつ、誰が、どのような行為を行い、どんな損害をもたらしたのか」を客観的に把握する作業が含まれます。
適切な調査が行われなければ、処分の妥当性が問われ、裁判で無効とされるケースもあるため、手順や証拠収集には細心の注意を払う必要があります。
ここでは、調査の進め方と対象の範囲について、具体的に見ていきましょう。
調査対象者の選定と証拠収集の手順
まず最初に行うべきは、調査対象者の選定と証拠の確保です。
直接的に不正行為を行った「本人」だけでなく、行為に関与した可能性のある複数の社員や関係者も含めて調査対象とします。
証拠収集で重視すべきポイント:
時系列に沿った行動履歴や業務記録の整理
デジタルデータ(パソコン、サーバー、メール)の解析と保全
日報や報告書、契約書類、レシート、社内申請書などの書類確認
調査は段階的に進めるのが理想的であり、いきなり本人に事情聴取を行うと、証拠隠滅のリスクが高まるため、先に客観的資料を整える段階が必要です。
また、証拠の収集にはフォレンジック調査が非常に有効です。
これは、専門の調査チームがデジタル機器から証拠を科学的に復元・分析する手法で、裁判でも通用する信頼性の高い資料を取得できます。
社内資料・メール・文書の解析
調査対象となる資料は、紙ベースとデジタルデータの両方にわたります。
特に重要なのが、メールのやり取り、文書ファイルの作成日時、ファイル名変更履歴などのデジタル記録です。
解析する主な資料の種類:
メールの送受信履歴(社内外)
文書ファイル(契約書、申請書、企画書など)
勤怠記録と打刻システムのログ
社内システムのアクセス履歴
パソコン操作ログと削除ファイルの復旧結果
これらを総合的に分析することで、不正行為が行われた「日時」「方法」「関係者」が明らかになり、後の懲戒処分や損害賠償請求の判断材料になります。
また、社内ルールの記載と実際の業務運用に乖離がある場合は、就業規則やマニュアルの見直しも求められます。
ヒアリングとアンケート調査の実施
証拠データと並行して行うべきなのが、関係者へのヒアリング(事情聴取)です。
ただし、これには慎重な対応と法的知識が必要であり、社内の担当者だけでなく、顧問弁護士や外部の専門家の同席が推奨されます。
ヒアリングの注意点:
脅迫や誘導と取られるような言動を避ける
事前に質問項目と目的を文書で作成しておく
複数名での同席により、証言の客観性を確保
録音や書面化による記録の残存
また、匿名のアンケート形式による社内調査も有効です。
社員の不安や社内風土に関するデータを集め、再発防止策の策定や改善に活用することができます。
不正発覚後の対応と懲戒処分の判断基準
調査により事実が明らかになった後、企業が次に行うべきは適切な対応と処分の実施です。
この段階では、社内外への影響や社員の権利、法的リスクを十分に検討しなければなりません。
対応を誤ると、企業側が不当な扱いをしたとして訴訟や損害賠償請求を受けることもあります。
この章では、不正行為が発覚した際に企業が取るべき対応と、処分判断の基準について解説します。
懲戒・解雇の法的判断と就業規則の整備
企業が従業員に対して行う処分には、戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇などの段階があります。
このうち、もっとも重い処分である「懲戒解雇」は、従業員にとって重大な不利益となるため、厳格な判断基準が必要です。
懲戒処分の判断基準例:
故意または重大な過失によって企業に損害を与えたか
法令違反、就業規則違反が明確であるか
社内の他の社員への影響や再発リスクがあるか
本人が過去にも同様の問題を起こしていないか
懲戒解雇を実施するには、以下の条件が整っていることが前提です:
就業規則に処分の根拠が明記されている
処分対象の行為が規定に該当している
客観的な証拠が存在し、事実関係が明らかである
社内での手続きを適正に経て、判断されたものである
就業規則の整備は企業が自らを守るためにも極めて重要です。
曖昧な規定では、懲戒処分が裁判で無効とされるリスクがあります。
法改正や判例を踏まえて、定期的な見直しと弁護士法人との連携が求められます。
弁護士との連携と処分文書の作成
処分を実施するにあたり、弁護士との連携は不可欠です。
特に懲戒処分や損害賠償請求を伴う場合には、法的手続きを誤ると逆に訴えられる可能性もあります。
企業が弁護士に依頼する主な業務:
処分の妥当性に関する法的判断
処分通知書や書面の作成・確認
関係者や通報者の保護方針の策定
損害賠償に関する訴訟手続きの代理
処分通知書や報告書には、次のような記載事項が含まれます:
処分対象の社員氏名と部門
実施する処分の種類と理由
調査の経緯と事実関係の要点
処分決定日と発効日
これらは、後に社内外への説明責任を果たす上でも極めて重要な文書となります。
文書の作成段階から顧問弁護士と協力することで、企業の法的リスクを最小限に抑えることが可能です。
損害賠償請求・民事裁判への発展ケース
従業員の不正行為によって企業が損害を受けた場合、損害賠償請求を行うことも選択肢の一つです。 たとえば、横領や情報漏洩による金銭的被害、不当な取引により失った契約などがこれに該当します。
損害賠償を請求する際は、以下のような要素を慎重に整理する必要があります:
被害の金額算定(売上減少、逸失利益、損害額の試算)
責任の所在と過失の有無
証拠資料の確保(契約書、記録、ヒアリング内容など)
関係者との対応履歴の記録
裁判に発展する場合は、弁護士の代理のもと、訴状提出から争訟手続きまでの対応が必要となります。 また、従業員が処分に対して無効を主張し、不当解雇として訴えるケースもあるため、事前に十分な準備と記録が求められます。
このように、調査の結果をもとに正当な処分と法的対応を行うためには、専門家との連携と企業法務に対する理解が不可欠です。
従業員不正防止のために企業ができること

従業員の不正は発覚した後の対応も重要ですが、何よりも重要なのは「未然に防ぐ仕組み」を企業として構築することです。 再発防止はもちろんのこと、日常的なコンプライアンス意識の醸成や内部統制の整備が、組織を守る強固な盾となります。
本章では、企業が取り組むべき不正防止策について、体制整備から具体的な社内施策まで幅広く解説します。
社内体制の整備と再発防止策の策定
不正の再発を防ぐためには、組織全体としてのリスク管理体制の整備が不可欠です。
この体制には、人事部門、監査部門、コンプライアンス担当、役員レベルのガバナンスチームまでが関与する必要があります。
整備すべき主な社内体制:
内部監査部門の設置・強化
コンプライアンス委員会の発足と運営
役員・経営層による監督・定期レビュー制度
全社員に対する研修制度の策定
また、不正行為が行われにくい環境をつくることも非常に重要です。
たとえば、「一人の社員に権限が集中している」「チェック機能が働いていない」といった状況では、不正が発生しやすくなります。
そのために必要なのが、業務フローの見直しと責任分担の明確化です。
具体的には、「入力・承認・管理・報告」の各段階に別の担当者を配置し、内部けん制の仕組みを導入することが望ましいです。
第三者委員会・監査チームの設置
社内調査や再発防止の取り組みにおいては、社内外からの客観的な視点を取り入れることが非常に効果的です。
その方法として近年注目されているのが、第三者委員会や外部監査チームの導入です。
第三者委員会の設置メリット:
社内の利害関係から離れた中立的立場での意見
調査報告書の客観性が高まり、外部への信頼性が向上
経営陣の判断をサポートする専門的な助言が得られる
監査法人や法律事務所と連携し、専門家を委員に加えることで、企業全体のガバナンスレベルが大きく向上します。
これらの取り組みは、株主やステークホルダーに対する説明責任にもつながり、社会的信頼の維持・向上に直結します。
社員・アルバイト・パートナーまで周知の徹底
不正を未然に防ぐ最大の鍵は「全員参加型のコンプライアンス文化」の醸成です。
それは正社員だけではなく、アルバイトや外部パートナーも含めた、組織全体でのルールの理解と共有が重要になります。
周知・研修における施策例:
定期的なコンプライアンス研修の実施(eラーニング含む)
就業規則・業務マニュアルの見直しと配布
社内イントラや掲示板での定期的な情報発信
アンケート調査による意識レベルの分析
また、内部通報制度の利用促進もポイントです。
社員が不正を見つけても「報告すると不利益を受けるのでは」と感じる組織では、どれだけ制度を整備しても機能しません。
そのため、公益通報者保護法への対応と共に、通報者の匿名性と保護を徹底し、報復を禁止する制度の明文化が必要です。
まとめ
従業員不正は、企業経営において避けて通れないリスクのひとつです。
どれほど信頼している社員であっても、不祥事を起こす可能性はゼロではありません。
それゆえに企業は、「うちに限っては起こらない」と油断するのではなく、常にリスクを想定し、備える姿勢が求められます。
これまで解説してきたとおり、従業員による不正には以下のような要因があります:
業務の属人化による監視の緩さ
コンプライアンス意識の不足
就業規則や社内制度の不備
取引先との癒着や社外との不透明な関係
金銭的なプレッシャーや個人的な感情による動機
これらに対して、企業が講じるべき対策は次のように整理できます:
内部監査体制の整備と役割の明確化
通報者保護制度の導入と運用の徹底
就業規則の見直しと処分基準の明文化
定期的なコンプライアンス研修と情報発信の実施
外部専門家との連携による早期対応と証拠保全
特に重要なのは、「不正が発生してから対応する」のではなく、「発生させない仕組み」を先に構築することです。
そのためには、従業員一人ひとりが法令と企業理念に則った行動を取るよう促す企業文化の醸成が欠かせません。
不正が疑われた際に、すぐに調査を始めるべきかどうか迷うこともあるでしょう。
そんなときには、信頼できる外部の専門家に相談することが、企業を守る最善の一手になります。
HAL探偵社では、企業の規模や業種を問わず、不正調査に特化したサポートを提供しています。
証拠収集から法的対応のアドバイス、再発防止策の提案までワンストップで対応可能です。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
HAL探偵社の浮気チェック
調査成功率97.3%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上